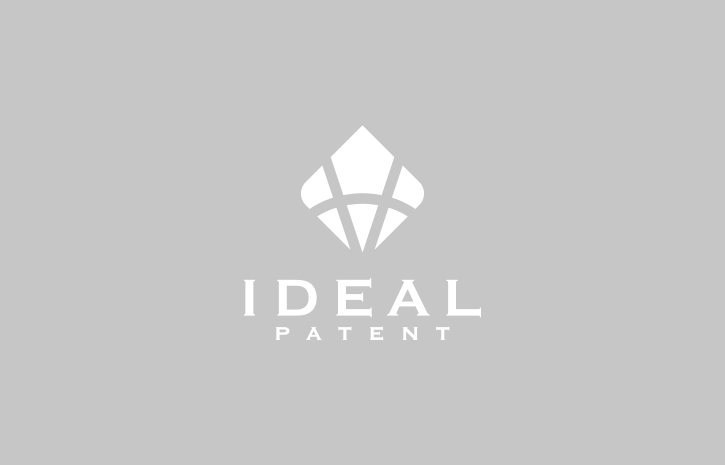
商標登録には落とし穴があります。実はひっかかっているかもしれません
商標は事業上絶対に意識しないといけないものの、商標の世間的な認知度はさほど高くありません。もっとも、最近では様々な商標事件により世の中における商標の認知度は上昇傾向にはあると思います。直近だとゆっくり茶番劇の大炎上が話題になりましたね。この事件をきっかけにYoutuberの商標出願が増加しているそうです。Youtuberの方々も事業でその名称を使っている以上、その名称を使えなくなると困りますからね。ですが、本来的にはこのような事件に巻き込まれる前に取り組んでほしいというのが弁理士目線での考えです。
事業を営んでいる人であれば、「商標登録」という言葉を聞いたことあると思います。商標登録とは、自社が商品・サービスに対して使用する商標を特許庁に登録することをいいます。特許庁に登録されることで、商標権者は商標権という権利を得られます。
なので、商標権者は、自分の商標を第三者が使用している場合に、商標権に基づいた権利行使を行うことができます。これにより、商標権者は登録した商標を独占的に使用することができるのです。
一方、商標登録は早い者勝ちなので、自分が商標登録を受けておらず、自社商標を誰かに商標登録されてしまった場合、その商標登録にかかる商標権の効力により自社商標を使えなくなってしまいます。こうなった場合かなり困ると思います。チラシ、名刺、HP等の各種営業資料も作り直しですし、ブランドの変更は顧客離れを意味します。このような事態を未然に防ぐために商標登録を行うべきなのです。加えて、商標を使用する前に、他人の商標権に抵触する範囲で使用することにならないかの調査をすることが大事です。このあたりは必ず商標の専門家である弁理士に相談しましょう。ご自身で調査を行って、その調査に誤りがあった場合に不利益を被ってしまうからです。
商標権の存続期間は設定登録の日から10年となっており、10年経過後に更新することができます。この更新は何度でも行うことができるため、商標権は半永久的な権利として認められています。一方、特許権や意匠権は権利の存続期間が決まっており、その存続期間が満了したときに権利が消滅します。商標権が特許権や意匠権と異なり、半永久的な権利として認められている理由は、商標法の保護対象にかかわってきます。
商標法は商標を保護するものですが、実際に保護する対象として商標法上認められているのは商標自体ではありません。つまり、商標法は、ネーミングやロゴマーク自体を保護対象としているものではないのです。商標法は、商標に対する需要者の信頼を保護対象としています。みなさんも好きなブランドありますよね。コンビニ、洋服、飲み物等、お気に入りのものがあるはずです。そのお気に入りという信頼を商標法は保護対象としています。この信頼は企業の営業努力によるものです。この営業努力によって生じた信頼自体を直接的に保護することはできませんよね。形があるものではないので。なので、商標法は、商標の保護を介して、実質的に需要者の信頼を保護しているのです。この信頼は長年の営業努力によって生まれたものであって、企業がこれを続ける限りは半永久的に存在しますよね。むしろ、その信頼は大きくなっていくはずです。にもかかわらず商標権の期限を設けることは商標法の意図に反してしまうのです。そのため、商標法は商標権の存続期間が満了したら何度でも更新可能として、商標権の半永久的な権利を認めているのです。なお、更新制度をなくして最初から永久的な権利として認めてまえばいいという考え方もあるものの、最初から半永久的な権利として認めてしまうと登録だけされている不使用商標が蓄積していってしまうので、10年で一旦区切って更新しようねという制度になっています。商標法には使っていないとその商標登録を取消すことのできる制度もあり、商標が使用されていることを前提としている法律なのです。
ここまでで、商標の概要については概ね理解できたかと思います。
商標登録を受けると、その商標が特許庁に登録され、商標権者に商標権が発生するということでしたね。では、登録商標を使用している第三者に対していかなる場合でも権利行使をすることが可能なのでしょうか?
答えはNOです。
商標権は権利です。なので、土地と同じように自分の権利と他人の権利との境界線をはっきりさせるための権利範囲というものが存在します。
商標権において権利範囲を決めるのは、①登録された商標と②指定商品・指定役務です。商標権は、①と②のセットで一つの権利ということになります。②の指定商品・指定役務とは、登録された商標の用途を指します。この用途は、自社が行っている事業の内容と整合するものを選択する必要があります。自社の商標を何の商品又はサービスに使用するかということですね。商標権の権利範囲は、指定した用途の範囲にのみ限定されます。したがって、商標登録したからといって、どの用途に対しても権利行使をすることはできません。
指定商品・指定役務は商標登録出願を行う際に決めて出願書類に記載します。そのため、出願前に自社の商品・サービスを整合性のある指定商品・指定役務を選ぶ必要があります。指定商品・指定役務は全部で45区分に分かれており、この区分の中から選びます。指定商品は1~34類、指定役務は35類~45類です。これが結構やっかいなもので、区分が違えば権利範囲が変わる場合もあり、慎重に選ぶ必要があります。例えば、オリジナルブランドで販売するハンカチと小売で販売するハンカチの区分は違います。オリジナルブランドで販売するハンカチの区分は第24類なのに対し、小売業で販売するハンカチの区分は第35類となります。
第24類は、織物や織物の代用品等に関する区分です。例えば、メリヤス生地、フェルト及び不織布、布製身の回り品、ふきん、シャワーカーテン等がここに入ります。
第35類は、人又は組織が提供するサービスに関する区分です。小売業はここに入りますが、小売を指定する場合は、小売販売する具体的な商品も含めて指定する必要があります。小売業全般だと権利範囲が広くなりすぎるため、このような運用となっています。
指定したい商品・役務の区分数が増えると、基本的に弁理士に支払う手数料と特許庁に納付する手数料が増加します。指定商品・指定役務の数が増えると権利範囲が広がるため、弁理士が事前調査する範囲と特許庁の審査官が審査する範囲が広がるためです。
なので、商材が多い場合は、優先度の高いものから商標登録を行う必要があります。雑貨屋さんでオリジナル商品が多い場合なんかだと結構大変ですね。オリジナル商品ごとに区分を指定する必要があるので結構な数の区分を指定することになります。「雑貨」という全ての商品を包含する抽象的な表現があればよいのですが。費用を抑えたい場合は、主力の商品のみ対応する区分を指定し、他の商品については35類の小売役務を指定するのも一つの手ですね。
一方、25類なんかだと複数の商品を一区分で出願できる場合もあります。25類は被服、履物、帽子等に関する区分です。被服の中には洋服、和服、寝巻き類、下着等が含まれます。履物の中にはスニーカー、革靴等の靴類、げた、運動用特殊靴等が含まれます。このように、複数の商品を権利範囲に含めたとしても、一つの区分で済む場合もありますので、そのあたりはケースバイケースですね。
いずれにしても、指定商品・指定役務の選び方には落とし穴があり、落とし穴に引っかかってしまった場合は、カバーしたい範囲の商標権を取得することができず、無意味な商標権を保有することになる可能性があるということです。








